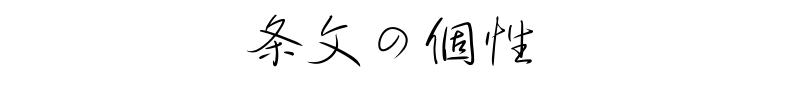本記事は,なぜ発行可能株式総数に最大4倍の上限制限が設けられているのか,について解説しています。
- ※赤文字は,行政書士試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方です
- ※太文字は,解説中で大切なポイントです
- ※本記事は2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
結論:発行可能株式総数の上限は,既存株主の権利保護のため
発行可能株式総数は,既存株主の保有株の希釈化を防止し,権利を保護するために存在する。
ただし,新たな株式を発行する際の判断を行うのが,原則として取締役会である公開会社にのみ,発行可能株式総数の上限制限が適用される。(非公開会社の判断は,株主総会の特別決議)
解説:発行可能株式総数は,絶対的登記事項として要求されるほど重要
株式会社は,自社の株式を新たに発行して,資金調達を行うことができます。
新たな株式が発行されるということは,発行株式の数や割合が変わることを意味し,既存の株主のパワーバランスの変動が発生します。
よって,無尽蔵に株式を発行出来たりすると,既存株主が経営権を失ったり,場合によっては会社を乗っ取られるリスクが存在します。
そこで,会社法は会社が発行できる株式の総数(発行可能株式総数)に上限を設けて,既存株主の権利を保護するルールを用意しています。
1 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 (本記事では略)
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
↓
1
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して株式会社は,株式会社の成立の時までに,絶対的登記事項として,発行可能株式総数の定めを設けなければならない。2 (本記事では略)
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
↓
1 株式会社は,株式会社の成立の時までに,絶対的登記事項として,発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 (本記事では略)
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
会社法37条
1 株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
2 (本記事では略)
3 次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。
一 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合
二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合
4 (本記事では略)
会社法113条
以上のように,絶対的登記事項に指定してまで,会社の設立までに必ず発行可能株式総数を定めることを法37条1項で要求をしています。
1 株式会社は,株式会社の成立の時までに,絶対的登記事項として,発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
会社法37条1項
さらに,会社が成立した後も法113条1項によって,発行可能株式総数の制限ルールを定款から削除できないようにしています。
1 株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
会社法113条1項
このように,発行可能株式総数は法37条1項と法113条1項の2つの条文を使ってまで,入念に制度設計をしています。
その理由は,既存株主の権利を厚く保護するためです。
発行可能株式総数を明確にしておくことで,仮に上限値まで株式が発行されても,「自分は最悪のケースでも〇%の割合は株式を保有できるな」という未来を,株主は見通すことができるようになるのです。
さて,発行可能株式総数の上限は設立時発行株式(設立後は発行済株式)の4倍まで,とされています。(たとえば,設立時に発行した株式が100株ならば,その会社が発行できる株式の最大値は400株です。)
これは,上限を定めなさいというルールが有っても,意味のある上限でなければ,上限を設けた趣旨が没却されるからです。
たとえば,上限を設けなければならないというルールだけでは,発行可能株式総数を1無量大数株というような天文学的な数にすることが可能です。
このような上限は,実質的には上限の役割を果たしておらず,実質上限が存在しないのと同じ状態になってしまいます。
そこで,上限の最大値を設立時に発行した株式の最大4倍まで,とすることで,将来の資金調達のニーズと,既存株主の保護とのバランスが取れるようになっているのです。
ただし,最大4倍制限が課されるのは,公開会社のみです。(法37条3項,法113条3項2号)
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
会社法37条3項
3 次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。
一 (略)
二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合
会社法113条3項
これは,非公開会社では募集株式を発行するのは,株主総会の特別決議が必要なので,ある程度は新株発行の影響を株主自身でコントロールできるからです。
一方の,公開会社では,募集株式の発行は取締役会の権限なので,株主自身で新株発行コントロールができないため,上限を設けることで,株主の権利を保護できるようにしているためです。
参考文献
この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。
行政書士合格を目指す方必見!
筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用書籍を無料公開しています。
特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!
合格への手段のひとつとして,予備校も視野に入れましょう!
法律系資格の合格の最短&最強ルートは,誰かに教えてもらうです。
最近はオンライン授業サービスを提供している予備校が多くなってきています。
スキマ時間を有効活用できるオンライン授業が,低価格で受講可能な予備校を有効活用して,自分自身のスキル習得へ,賢く投資していきましょう。
資料請求や相談面談はどこも無料なので,まずは気軽に資料請求から,合格に向けて一歩踏み出しましょう。
最後まで読んでくださりありがとうございました!