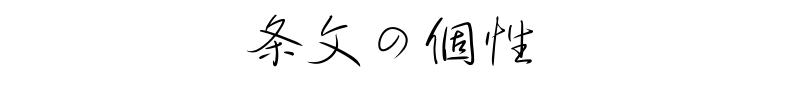内閣は三権分立で分割された権力のうちの1つである行政権を担当する組織でした。
働いている人たちは国会議員の中から選ばれた内閣総理大臣と国務大臣たち約15名です。
行政権はとても広い範囲の権力が及ぶため、専門家の間でもどこまで行政権という権力のチカラを認めるのか意見が割れています。
ざっくりとした説明になってしまいますが、全ての国家権力のうち立法権・司法権以外の残った権力=行政権と思って頂いてOKです。(控除説)
市役所で手続きしたり、自衛隊を出動させたり、外国と条約を結んだり、学校を作ったりなどなど…あれもこれも行政権のチカラです。
あまりに広範囲をカバーしている内閣という組織はどのようにして仕事をしているのか。 また、内閣がどのような仕事を担当しているのか、今回は見ていきましょう。
内閣の仕事
内閣が関わる分野はあまりに大きすぎます。
なので今回は受験で憶えておくべき・常識として知っておくべき部分にフォーカスしてお話します。
内閣は行政を行うわけですが、まず簡単に行政のイメージだけつかんでおきましょう。
行政とは、国会が作った法律・承認した予算の中で政治を行うことです。
その中でも試験でよく出る点を以下にまとめます。
法律案や予算を作成し、国会に提出する
あれ?法律や予算は国会が作るんじゃないの?と思ったかも知れません。 ここは勘違いしやすいのでしっかり整理しましょう。
まず、法律の原案は内閣でも作れます。 内閣から出された原案をもとにして、国会が法律にするべきか審議します。
「これはきちんと法律にすべきだ!」と国会が判断したら、国会が正式な法律として作っていくのです。
ですから、内閣も法律の元ネタは提案することができるのです。
次に、予算の原案は内閣が作ります。 予算ってのは国が1年間に使えるお金を何に使うかの計画表みたいなものです。
自衛隊に1000億円、新しい道路を作るのに10億円、皆さんの教科書代に15億円使って…あとは…と内閣が原案を作ります。
そして、その原案が通常国会で内閣から国会に提出されます。
その後、全国の国会議員たちが日本のお金をどのように使うのか相談して決めて、国会が予算の決定版を完成させます。
外国と条約を結んだり、外交取引をする
今、世界には(日本が国と認めた数で)200弱の国が存在しています。
私たち日本も海外のいろんな国と協力し合っていかなければいけません。 国と国とが貿易したり、お金を貸しあったりなど協力することを外交取引と言います。
協力すると言っても、ただの口約束で国同士でお金を貸し合ったり、するのはかなりリスクがあります。
みなさんの周りの友人を思い浮かべてみてください。
友人の中には、しっかりしてる人・いい加減な人・乱暴な人・優しい人…色々いると思います。
国も同じで、日本のように戦争はしませんよと平和主義の国も有れば、積極的に周りの国に戦争をふっかけている国もあります。
国が約束を守ってくれるかどうかは、人との約束と同じかそれ以上にわからないのです。
なので、国と国の約束ごとは書面で交わして約束内容を証拠とし残して「条約」という形で約束をします。
条約は国と国の約束ごとですが、約束・決まり事を破ればだいたいペナルティが有ります。 罰金とか貿易の取引中止とかですね。
決まり事を違反したらペナルティ…何かに似ていると思いませんか?
そう、法律です。
法律と条約はとても似ています。 違いは、法律は日本国内の決まり事のこと、条約は日本と外国との国の外側の決まり事という点です。
しっかり違いを抑えておきましょう。
内閣は条約を外国と結び、外交取引をする役割と権力を担当しています。 立法権も司法権も日本国内に関することがメインです。
内閣の持つ行政権は外交取引も権力が及ぶため、日本国外に関しても影響力を持つ組織ということになります。
これだけでも内閣が担当する範囲が、国会や裁判所よりはるかに大きいことがわかりますね。
国会を召集する
ここで言う国会は会議の意味の国会です。 国会で会議するよー!と、内閣が日本全国の国会議員を集めます。
「会議の意味の国会」がピンと来ない方はこちらを読んでみてください。
衆議院の解散を決定する
内閣のリーダーである内閣総理大臣は基本的に衆議院議員なので、衆議院と運命共同体です。
衆議院の解散は次の2通りのパターンがあります。
- 内閣不信任案が国会から提出され、内閣が衆議院解散をさせる
- 衆議院の任期4年が経ち、形式的に解散する
以上のどちらのパターンでも、正式に衆議院の解散の効果を発動するために、内閣が解散を発表します。
天皇の国事行為に対し、助言と承認を与える
日本国憲法においては、天皇は日本の象徴という立場なので国の政治に参加することができません。
逆に、政治には参加できませんが、形式的なお言葉や儀礼的な(法律の)公布などは行ってもらう必要があります。 このような政治的意図が無い、形式的な天皇の行為を「天皇の国事行為」と言います。
天皇に対して助言と承認を内閣が与えることで、「この国事行為には、天皇の政治的意図はありませんよ! 内閣が保証します!」とアピールしているという仕組みです。
政令の制定
政令とは、内閣が制定する命令です。
ものすごーく簡単に説明すると、法律の次に強い法的拘束力を持つ決まりごとです。
憲法>法律>政令という力関係の法的に力を持った命令です。
あれ? 法律って立法権を持つ国会しか作れないんじゃなかったっけ?と思ったあなたはとてもするどい。
そうなんです。 この「政令」という存在がなかなか厄介なのです。
事実上、法律とほぼ同じものである政令を内閣が作ることができるということは、内閣が立法権を侵食しているということです。
さらに三権分立を内閣がおびやかす仕組みが、実は司法権にもあります。
最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命
裁判所の中で一番上である最高裁判所のトップを誰が務めるかは内閣総理大臣が選んで指名します。
そして指名された人を最高裁判所長官と呼びます。
選ばれた最高裁判所長官は一緒に最高裁判所を運営する裁判官を選び、内閣が選ばれた裁判官を任命します。
しかし、ちょっと考えてみると少し不思議な仕組みではないでしょうか?
行政権という三権分立の中で最も力が大きい権力を持つ内閣が、司法権を担当する裁判所のトップを選んで指名するのです。
つまり、内閣は自分たちに都合の良い裁判官を選んで司法権を(間接的に)コントロールできるとも言えます。
裁判官側からすると内閣に有利な判決をすると出世しやすいとも言えます。 事実、最高裁判所の判決は内閣寄りなことが多いです。
内閣の力が司法権を侵食してしまっている仕組みとも言えますね。
実はアンバランスな三権分立
政令や最高裁判所長官の指名に関して正しい・間違っているは別として、このような仕組みを皆さんがどのように考えるかが大切です。
私たちは国民主権の日本で生きています。
おかしい・間違っていると思ったり、もっとこうすればいい!という意見が有れば、私たちには日本国憲法を変える権利があるのですから。