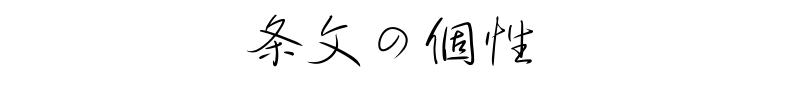今回は,民法5条を3分でわかりやすく解説します。
※当シリーズは条文が持つ効力を個性として捉えた表現で解説しています
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
民法 第5条【未成年者の法律行為】
条文の性格
民法1条~4条までのシンプルさと比べて一転、いきなり文字数が増えて複雑な条文となりました。
民法4条が,「お前は未成年!お前は成年!」と分類した未成年側の人達を,実際にどのように保護するのか?を,この民法5条が定めています。
民法5条は、未成年がした契約などの法律行為を取り消せるルールを用意し、知識や判断能力がまだ未熟な未成年を、不利益から守る役割を果たします。
民法4条が,未成年として保護する対象を定め,この民法5条が実際に保護する。
”あ・うん”の連携が美しい条文ですね。
条文の能力
1項:大原則 未成年は法定代理人の同意がないと法律行為ができない
5条1項は大原則として、未成年は法定代理人の同意がないと法律行為ができないルールがあること前提に書かれています。
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
民法 第5条1項【未成年者の法律行為】
この大原則をしっかり頭に入れておきましょう。
この大原則のもと、5条1項は原則の例外を以下の2つ定めています。
- ①法定代理人の同意があれば、未成年がした法律行為も有効とする(民法5条1項本文)
- ②単に権利を得、又は義務を免れる、未成年がした法律行為は有効とする(民法5条1項ただし書き)
法定代理人の同意があれば、未成年がした法律行為も有効とする
法定代理人とは、ざっくり言うと親権者・両親・保護者とイメージして頂ければOKです。
原則、未成年はひとりでは法律行為をできませんが、法定代理人すなわち親御さんが「いいよ」と同意した法律行為は未成年がひとりで有効にできるよ、ということです。
未成年がした、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為は有効とする
単に権利を得、又は義務を免れる法律行為とは、お金やプレゼントを貰ったり(所有権という権利を得る)、借りてたゲームを返さなくていいよ(返還義務を免除される)ような行為のことです。
これらは、未成年にとってメリットしかなく、損をする心配が無いので、いちいち法律行為が有効だの有効じゃないだの考えなくても一律有効でええやん、とされています。
2項:法定代理人(親御さん)の同意がない法律行為は取り消せる
5条2項に「前項(5条1項)の規定に反する法律行為は、取り消すことができる」とあります。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
民法 第5条2項【未成年者の法律行為】
つまり,法定代理人の同意がない未成年がした法律行為は,取り消せるということです。
3項:1項の原則の例外規定
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
民法 第5条3項【未成年者の法律行為】

条文読んだけど...
結局、目的を定めてても定めてなくても同じじゃね?
この5条3項は,初見だと混乱すると思います。
順を追って整理してみましょう。
まず、A.法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の例は、「これで参考書を買いなさい」とか「これで定期券を買いなさい」と使い道を指定して渡したお金などです。
次に、B.法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産の例は、お小遣いです。(月3,000円渡すが、使い道はおやつでもソシャゲ課金でもスパチャでも自由という財産)
そして,5条3項が言っているのは、5条1項の大原則関係なく、Aの場合は定めた目的の範囲内なら、Bの場合は完全に自由に、法定代理人の同意なく、未成年者は好きに財産を使って良いということです。
さて、3項はなぜこんなまわりくどい書き方がされているのかですが...。
実は、「法定代理人が使い道の目的を定めて財産を渡したのに、その目的の範囲外で未成年者が財産を使用したパターン」は、5条3項のA&Bの両方の場合に含まれていません。
つまり言い換えると、定めた目的の範囲外では、未成年は自由に財産を処分することを許されていないということです。
例えば、スマホ購入代金としてお金を渡したのに、勝手にPS5を買ってきたパターンです。
上の例では、5条3項に該当しないので、5条1項で原則&同意の有無で判断されることになります。
PS5にお金を使うことに法定代理人は同意してないわけですから、未成年者がしたPS5の売買契約は5条2項によって取り消すことができる契約になります。
このようにパターン分けをするために、少しまわりくどい書き方がされています。
筆者コメント
5条もそうですが、条文は原則→例外という書き方がされていることが多いです。
条文の構成だけでなく、法律を学ぶ上で原則をしっかり抑えた上で、例外を学んでいくという流れはとても大切ですので意識して勉強すると良いと思います。
※前条の解説はこちらです。
※次条の解説はこちらです。
参考文献など
参考文献
この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。
行政書士合格を目指す方必見!
筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用テキストを無料公開しています。
特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!
最後まで読んでくださり,ありがとうございました。