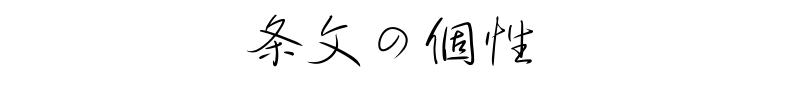今回は民法100条を3分でわかりやすく解説します。
※当シリーズは条文が持つ効力を個性として捉えた表現で解説しています
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語です
※太文字は,解説中で大切なポイントです
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
民法 第100条【本人のためにすることを示さない意思表示】
条文の性格
民法の第100条は,代理の発動条件を定めた同99条のサポート役です。
99条に規定された代理の発動条件の中に顕名というものがありました。
顕名とは,代理人が代理として意思表示をしていることを相手方に知らせることです。
意思表示は本来,その意思表示をした本人が自分のためにするものです。
コンビニで「これください」と商品を出して来た人がいれば,店員は「あ,この人が買うんだな」と普通は考えます。
車屋に来た人が「このレクサス買います」と申し出てくれば,当然にその人がレクサスを買うものと考えるでしょう。
そのため,代理人の意思表示効果が代理人に対してではなく,代理を依頼した人に発生させるために,99条は代理行為の成立に顕名を要求しました。
ここで,改めて99条をよ~く読んでみましょう。
1 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
民法 第99条 【代理行為の要件及び効果】
民法99条に書かれていることは「代理行為は顕名が有る場合に成立するよ」です。
反対に解釈すれば,顕名が無い代理行為は代理とはならない,と言えます。
ここで問題となるのが,99条の文言だけでは「顕名が有る場合の代理行為の効果は本人,顕名が無い場合の代理行為の効果は誰に帰属するの??」という疑問が残っているのです。
この疑問を解決するのが,顕名が無い場合の代理行為の効果の帰属先を定める100条です。
100条が99条の足りない部分を補っている,まさにサポート役なわけです。
条文の能力
100条本文:顕名無き代理行為の効果は,代理行為をした人に帰属する
顕名が無い場合の代理行為の効果は,顕名無く代理行為をした代理人に帰属します。
そんなん当たり前じゃね?と思うかもしれませんが,もし100条が無ければ顕名無き代理行為の効果がいったい誰に帰属するのか宙ぶらりんになってしまいます。
そのため,100条が必要なのです。
100条但し書き:顕名無き代理行為の相手方が悪意又は有過失なら,代理を依頼した人に効果が帰属
顕名の無い代理行為があったとしても,相手方がその意思表示が代理行為であることを知っていたか,又は普通代理だってわかるよね的な過失が相手方にあった場合は,代理を依頼した人に効果が帰属します。
すなわち顕名が無い意思表示の場合は,普通,相手方は意思表示した人に効果が及ぶだろうと考えますし期待します。
この相手方の期待を保護してあげようというのが100条本文です。
ところが,この保護してあげようとしている相手方が,代理行為であること知っていたか知ることができたのなら,わざわざ保護する必要は無いので,代理行為が成立したと同じ効果を発動させても良いだろうという設計になっています。
コメント
100条が定めていることは,仮に知らなかったとしても何となく常識に一致しているのではないでしょうか?
意外と民法は常識に沿って作られていたりするので,もし試験などでどうしてもわからなかったときは一度常識で考えてみるのもひとつの手です。
解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!
※前条の解説はこちらです。
※次条の解説はこちらです。