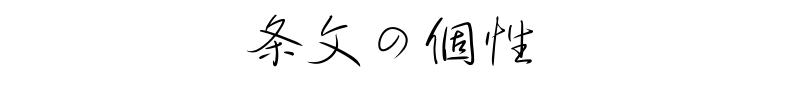今回は民法86条を3分でわかりやすく解説します。
※当シリーズは条文が持つ効力を個性として捉えた表現で解説しています
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
民法 第86条【不動産及び動産】
条文の性格
小中高で学年が上がる時の一大イベントといえばクラス替えですよね。
好きなあの子・あの人と同じクラスになれるのかワクワクしたり、仲のいい友達と離れ離れになって新たな人間関係構築に向けてドキドキしたり、一喜一憂の瞬間ですよね。
どうやらクラス替えは完全なランダムではないらしいですね、実際は色々と先生たちで相談して決めてるんでしょうかね。
さて、民法86条はそんなクラス分けを担当する条文です。
民法85条によって物として認められた生徒たちを、物の中で更に不動産と動産という2つのクラスに分けます。
つまり、この世の全ての物は不動産か動産の必ずどちらかに分類されて所属することになります。
ところで、ハリポッターの組み分け帽子は皆さんご存知でしょうか?
ホグワーツ魔法学校に入学してきた生徒が6年間所属する寮(クラス)を指定する役割を持つ、生きた帽子ですね。
あの組み分け帽子がやっていた
「スリザリンッッッ!」とか
「レイブンクロォォォー!」とか
「グリフィンドォォォルゥ!」とか
言ってたやつですね。
ハリポタの組み分け帽子と同じように、民法86条は85条によって物として認められて物の世界に入門してきたモノ(物?者?)たちを
「ふどぉぉさぁぁんんん!」とか
「どうさぁぁぁんんん!」とか
言って分類する感じの条文です。
もう忘れませんね。
86条の役割を今日しっかり憶えてしまいましょう。
条文の能力
物は不動産か動産の必ずどっちか
85条によって物として認められた有体物は必ず不動産か動産のどちらかに分類されます。
不動産
不動産というのは、土地や土地に定着している物のことです。
土地にくっついているので字の如く、動かすことの出来ない財産のことです。
土地に定着している物の例は、建物や立木や橋や(移動させることが難しい)庭石のことです。 つまり、これら定着物も不動産ということです。
原則、定着物は土地と分離できませんので、土地の売買などで所有権の移動が有った場合は、土地の所有権移動に付従する運命共同体となる特徴があります。
この運命共同体の性質は主物と従物の関係から来るのですが、その解説は以下でしてますのでよければ合わせて読んでみてください。
動産
逆に不動産でないものは全て動産となります。(86条2項)
つまり、土地や土地の定着物では無い物は全て動産です。
スマホ、PC、本、服、車、ボールペン、カップ麺、箸、電球、冷蔵庫、自転車などなど、世の中の大半は動産です。
※不動産投資なんて言葉があるので、不動産=高額な資産的なイメージがありますが、どんなに高額でも、土地及びその定着物でないなら動産です。 めちゃくちゃ高額なフェラーリやランボルギーニでも動産です。
定着物だけど土地とは別の不動産扱いになる例外
土地にくっついている定着物は土地の一部として扱われる。
これが原則です。
ただし、土地にくっついている定着物であっても、その土地の一部とせずに別の不動産として扱う例外がいくつかありますので確認しましょう。
①建物
土地Aの上に建物Bが建っている場合、土地Aと建物Bは別の不動産という扱いになります。
つまり、土地Aと建物Bを持っていて、建物Bだけ売るなんてことが可能です。
②登記された立木
立木も、立木法という法律に従って登記することができます。
登記した立木は土地にくっついてますが、土地とは別の独立した不動産として扱われます。
コメント
なぜ不動産と動産をクラス分けするのかですが、民法自身が、取引する目的物が不動産か動産かで色々とルールを分けているからです。
細かいルールは各条文での解説に託しますが、以下のことを頭の片隅に入れておくと民法の物権理解に役立ちます。
- 不動産は高額な取引なので1件1件の取引の安全を優先し、取引する人にしっかり確認や手続きを行うことを要求する
- 動産は比較的少額な取引で、実社会で大量に取引が行われているので、簡易的なやり取りで取引を認める
ここだけを読んでも理解は難しいかもしれませんが、このメインストリームを頭の片隅に入れて勉強すると助けになることも多いと思いますので、抑えておきましょう。