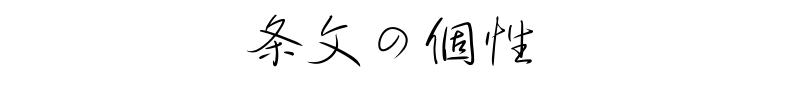なんかテキストを読んでいたらいきなり「現実の提供」「口頭の提供」って出てきたんですけど?!
これなに?!
本記事では,弁済の提供をする方法である「現実の提供」「口頭の提供」について,わかりやすく解説しています。
本記事を読むことで,以下を達成できるように執筆しています。
- 現実の提供・口頭の提供について基礎から理解できる
- 重要判例である最大判昭32.6.5を理解できる
記事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち
読者さんへの前置き
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
※本ブログでは,記事内容を要約したものを先に【結論】としてまとめ,その後【解説】で詳細に説明をしていますので,読者さまの用途に合わせて柔軟にご利用ください!!
結論:弁済の提供の方法は2種類
民法493条 【弁済の提供の方法】
弁済の提供は,①債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし,債権者があらかじめその受領を拒み,又は債務の履行について債権者の行為を要するときは,②弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
民法では,民法493条にて,弁済の提供として以下の2種類を認めています。
- ①現実の提供
- ②口頭の提供
現実の提供とは,債権者の協力以外の,弁済をするについて,債務者がするべきすべてのことを行うことです。
口頭の提供とは,弁済の準備をしたことを債権者に通知して,その受領の催告をすることです。
弁済の準備とは,債権者がやっぱり受領するわ,と心変わりした際に,債権者が受領しようと思えば,債務者側で給付を完了できる程度の用意のことです。
弁済の提供は,原則は現実の提供で行うこととなります。
例外として,債権者があらかじめその受領を拒み,又は債務の履行について債権者の行為を要するとき,口頭の提供をもって弁済の提供があったと扱われます。
さらに,判例(最大判昭32.6.5)により,債権者が受領しないことを終局的・明確的に表明している場合は,口頭の提供すら不要とされています。
法は無駄・無意味なことを要求するものではないため,無意味になることが確定している口頭の提供を,債務者に要求せず,口頭の提供すら不要という趣旨の判決です。
解説:原則→現実の提供 例外→口頭の提供
※本記事は,民法473条【弁済】と民法492条【弁済の提供の効果】の内容を正確に理解している前提で書かれています! 数分で読める内容ですので,是非先に目を通してから戻ってきてみてください!
弁済の提供は2種類存在する
弁済タイミングよりも前の段階で,債務者を義務から解放する制度である弁済の提供ですが,では一体なにをすれば弁済の提供と扱われるのでしょうか?
民法では,民法493条にて,弁済の提供として以下の2種類を認めています。
- ①現実の提供
- ②口頭の提供
民法493条 【弁済の提供の方法】
弁済の提供は,①債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし,債権者があらかじめその受領を拒み,又は債務の履行について債権者の行為を要するときは,②弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
ここからは,現実の提供と口頭の提供について,詳しく確認していきましょう。
①現実の提供(原則)
民法493条 【弁済の提供の方法】
弁済の提供は,①債務の本旨に従って現実にしなければならない。
現実の提供とは,債権者の協力以外の,弁済をするについて,債務者がするべきすべてのことを行うことです。
つまり,商品を債権者の家で渡す債務の場合,商品を用意し,約束の日時に実際に債権者の家に行き,物を持参し,インターホンを押すところまでが,現実の提供となります。
あとは債権者が受領さえしてくれれば,弁済が完成するので,債務者はできることを全てやっていると言えるため,『①債務の本旨に従って現実にし』たこととなり,現実の提供として認められます。
②口頭の提供(例外)
民法493条ただし書き 【弁済の提供の方法】
ただし,債権者があらかじめその受領を拒み,又は債務の履行について債権者の行為を要するときは,②弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
口頭の提供とは,弁済の準備をしたことを債権者に通知して,その受領の催告をすることです。
弁済の準備とは,債権者がやっぱり受領するわ,と心変わりした際に,債権者が受領しようと思えば,債務者側で給付を完了できる程度の用意のことです。
弁済の提供は,現実の提供で行うことが原則となります。
しかし,以下の2パターンのどちらかに該当するならば,口頭の提供をもって弁済の提供の完成を認めようという例外が民法には用意されています。
- パターンⅠ:債権者があらかじめ受領を拒んでいるとき
- パターンⅡ:債務の履行について債権者の行為を要するとき
民法493条ただし書き 【弁済の提供の方法】
ただし,(Ⅰ)債権者があらかじめその受領を拒み,又は(Ⅱ)債務の履行について債権者の行為を要するときは,②弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
(※ここから弁済=①提供+②受領の式を用いて説明します!)
パターンⅠは,債権者が「受領(②)をしませんよ~」と態度を示しているならば,現実の提供をしても,弁済=①提供+②受領が完成しないのですから,現実の提供まで債務者に求めないでよいだろうという趣旨です。
前述の,商品を債権者の家で渡す債務の場合で,債権者があらかじめ受領を拒否しているならば,債務者は商品を債権者の家まで持って行く必要が無く,準備したうえで「いつでも商品持って行けるよ~ん」と通知すればOKです。
パターンⅡは,債務の履行について債権者の行為を要するのであれば,債権者の協力が無ければ弁済が完成することはないため,現実の提供までは要求せず,債務者を義務から解放するポイントをもう少し前の口頭の提供でよいだろうとする趣旨です。
ここで言う『債権者の行為』とは,債権者が,所有している農地を売買できるようにするために,農地委員会からの許可を得る,というような行為のことです。(※農地は基本的に自由に売買できないので,この実務上の知識は試験対策としておさえておいてください!)
つまり,弁済=①提供+②受領+③債権者が許可取得する,という式となり,②③は債権者側のアクションですので,①の準備が出来たという通知をすることまでで債務者としては必要なアクションを起こしたと評価できます。
よって,民法は債権者の行為を要する場合は,現実の提供まで要求せず,口頭の提供をもって債務者を義務から解放する設計とされています。
重要判例:最大判昭32.6.5
なお,口頭の提供のパターンⅡにおいては,大事な判例(最大判昭32.6.5)があります。
判例(最大判昭32.6.5)により,債権者が受領しないことを終局的・明確的に表明している場合は,口頭の提供すら不要とされています。

ん?
口頭の提供が必要とされる民法493条ただし書きパターンⅠと何が違うんですか?
パターンⅠも,『債権者があらかじめ受領を拒んでいるとき』ですよね?
はい,大事なのは『終局的』という部分です。
終局的に受領しないということは,天地がひっくり返っても債権者は受領しないと言っているのです。
エターナル・フォーエバーです。
未来永劫,弁済に必要な受領(②)が揃わないことが確定しているのです。
そして,口頭の提供といえども準備&通知が必要であり,大なり小なり債務者にも手間がかかります。
なのに,弁済に必要な受領(②)が揃わないことが確定している状況で,多少なりの手間がかかる口頭の提供を必要としてしまうと,全く無駄な口頭の提供作業を債務者に課すことになります。
法は無駄・無意味なことを要求するものではないため,無意味になることが確定している口頭の提供を,債務者に要求せず,口頭の提供すら不要という趣旨の判決です。
解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!
※前条の解説はこちらです。
※次条の解説はこちらです。
※本記事と関連性の高い記事をあわせて読んで,学習効率UPしていってください!
※当ブログの人気記事です! 是非あわせて読んでみてください!
参考文献など
参考文献
この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。
行政書士合格を目指す方必見!
筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用テキストを無料公開しています。
特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!
最後まで読んでくださり,ありがとうございました。