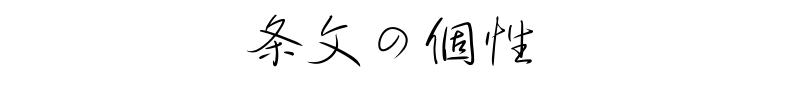地上権は,設定するに際して存続期間を定めることは必須ではないですよね?
なら,存続期間を定めなかった場合,地上権設定関係を終了したい当事者たちはどのようなことが出来るのですか?
地上権者は,いきなり地上権を放棄させられたりするような事態に陥るの?
本記事は,民法268条の,地上権の存続期間について,その原則と例外に整理して,わかりやすく解説しています。
事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログの管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発(202点)で行政書士試験に合格した勉強法
参考:筆者を4ヶ月で合格に導いた超厳選の良書たち
読者さんへの前置き
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
結論:地上権者が,地上権を突然失うことの無いように配慮されている
1 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。
民法268条 【地上権の存続期間】
地上権の存続期間が定められていない場合,以下の原則・例外に従って,地上権者・地上権設定者はアクションを起こすことができます。
【前提】
地上権が設定されているが,その存続期間について定めがない。
【原則】
地上権者は,いつでも地上権を放棄できる。
(理由)地上権は物権であるので,その処分も自由にできるはずであるから。
【例外①:地代の支払いがある】
地上権者は,いつでも地上権を放棄できるが,1年前に予告する又は1年分の地代を支払わなければ,地上権を放棄できない。
(理由)今後もしばらく地代による収益を見込んでいる地上権設定者の期待を保護するため。
【例外②:地上権者が地上権を放棄する気がない】
当事者(地上権者・地上権設定者のいずれか)からの請求で,裁判所が,一切の事情を考慮して,20~50年の範囲内で,存続期間を定める。
(理由)地上権者が地上権を放棄する気がなく,存続期間に定めがない場合だと,実質的に永久に現状を解決することができなくなってしまう。
※地上権という権利自体については,以下の記事で解説しています。 ぜひ併せて読んでみてください。
※地上権の存続期間が永久設定が可能かどうかは,以下の記事で解説しています。 ぜひ併せて読んでみてください。
解説:原則と例外を整理し,地上権者・地上権設定者の双方に配慮されていることを理解する
民法268条は,存続期間を定めずに地上権が設定されている状況において,地上権者と地上権設定者の利害関係を調整するための規定です。
地上権は物権であるため,地上権は排他性を有します。
地上権という物権を持つ地上権者は,誰にも邪魔されず(=排他性)に,自由に地上権を設定した土地を使用できます。
それは,“地上権を放棄する”という,地上権を処分するかしないかも,地上権者次第ということです。
したがって,地上権が一旦成立すると,地上権設定者は,地上権者から地上権を取り上げることはかなり難しい立場になります。
他人の土地を借りるのが地上権ですが,借りている側の地上権者の方が圧倒的に強い立場になるのです。
そんな,パワーバランスが圧倒的に”地上権者>地上権設定者”である状況では,地上権の存続期間の定めがないとき,“既に成立している地上権の存続期間をどうするか”を決定するにおいても,地上権者の方が強い立場になります。
自身が持つ地上権という物権の存続期間を定めないのか,定めるのか,定めるにしてもいつまで存続させるのか,を決めるのも“地上権の処分”と言え,それは地上権という物権を所持する地上権者次第だからです。
そうなると,地上権者が,地上権の放棄か,地上権に存続期間を設定することに同意をしてくれなければ,地上権設定者は土地を取り戻すことが実質的に永久に不可能になってしまいます。
そこで,民法285条の出番で,地上権・地上権設定者の双方に配慮したかたちで,以下のとおり【原則】【例外①】【例外②】の3通りのアクションをできるようにし,利害関係を調整しています。
【原則】
地上権者は,いつでも地上権を放棄できる。
【例外①:地代の支払いがある状況】
地上権者は,いつでも地上権を放棄できるが,1年前に予告する又は1年分の地代を支払わなければ,地上権を放棄できない。
【例外②:地上権者が地上権を放棄する気がない状況】
当事者(地上権者・地上権設定者のいずれか)からの請求で,裁判所が,一切の事情を考慮して,20~50年の範囲内で,存続期間を定める。
【原則】
大原則として,存続期間が定められていないなら,地上権者は,いつでも地上権を放棄できます。
地上権者は,地上権という物権の所有者であるので,地上権を放棄することも当然できるはずだからです。
【例外①:地代の支払いがある状況】
地上権者は,いつでも地上権を放棄できますが,地代の支払いがある場合は,1年前に予告する又は1年分の地代を支払わなければ,地上権を放棄できません。
地代の支払いがある場合,その地代の支払いで生活が厳しいなどの状況もあり得るため,地上権者はいつでも地上権を放棄して,その地代支払の義務から解放できるようにしてあります。(ここは原則通りです)
ただ,地役権設定者は“今後も地代の支払いは継続されるだろう”という収益の見込みを立てていることが多く,また,土地の地代は(家賃などと比較して)高額であることが多いため,いきなり収益が無くなると生活基盤が脅かされるおそれがあります。
そこで,地上権者の権利放棄について,1年前の予告か,1年分の地代の支払いの義務を課し,地上権設定者を保護しています。
【例外②:地上権者が地上権を放棄する気がない状況】
地上権者が地上権を放棄しない意思を有している場合,当事者(地上権者・地上権設定者のいずれか)からの請求で,裁判所が,一切の事情を考慮して,20~50年の範囲内で,存続期間を定めることになります。
地上権の存続期間がなく(時が解決してくれない),地上権者が地上権を放棄する気がない(権利者が譲らない)という状況は,実質的に永久に土地を地上権者に奪われた事態に陥っています。
そこで,当事者(地上権者・地上権設定者のいずれか)からの請求で,裁判所が仲裁に入り,事態を解決することができるようになっています。
勘違いしやすいポイントですが,裁判所へ存続期間を定めてくれって請求できるのは,“当事者”であるので,“地上権設定者だけでなく,地上権者も請求できる”という点に気をつけてください。
たとえば,
「存続期間を定めてなかったけど,地上権設定者が『地上権を放棄しろ!』としつこいねん。 しばらくは,地上権が必要だから,裁判所さん,しばらく使えるように存続期間をとりあえず定めてや~。」
というように,地上権者も裁判所へ請求可能です。
解説はここまでです。 読んで頂きありがとうございました!
参考文献など
参考文献
この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。
行政書士合格を目指す方必見!
筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用テキストを無料公開しています。
特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!
最後まで読んでくださり,ありがとうございました。