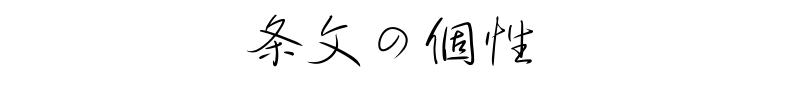今回は民法92条を3分でわかりやすく解説します。
※当シリーズは条文が持つ効力を個性として捉えた表現で解説しています
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語です
※太文字は,解説中で大切なポイントです
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において,法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは,その慣習に従う。
民法 第92条【任意規定と異なる慣習】
条文の性格
民法92条は、民法91条の兄弟(姉妹)みたいなものです。
公の秩序に関しない規定、すなわち任意規定として法律に定められたルールとは違った慣習が有れば、それにしたがっていいよと言ってます。
民法91条や任意規定についてはこちらを読んでみてください。
つまり、慣習>民法ということで、民法91条と同じくルール破壊の条文です。
個人的な92条のイメージは、アニメとかによく出てくる、田舎の村の掟を教えてくれるおじいちゃん・おばあちゃんでしょうか。
「この村には○○という掟(=慣習)があるんじゃ。 郷に入れば郷に従わないかん」みたいな感じです。
条文の能力
もう一度、民法92条を見てみましょう。
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において,法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは,その慣習に従う。
民法 第92条【任意規定と異なる慣習】
民法92条の条文をよく読むとわかるのですが、「民法の任意規定と違う慣習が有るなら、その慣習に絶対従え」とは言っていません。
「民法の任意規定と違う慣習があって、かつ、当事者達がその慣習に従うとしているときに、その慣習に従ってええで。」と言っています。
コメント
ちなみにですが(多分、行政書士試験にも宅建試験にも出ない)、「その慣習による意思を有しているものと認められる」とは、積極的に「慣習に従おうぜ!」って言わなくてもよいとされてます。
つまり「その慣習には従わないぜ!」と言わない限り、黙っていると、慣習に従っていると推定されます。
ちなみにのちなみに、「みなす」と「推定」の違いを知らないあやふやな人はこちらの記事で解説しているので併せて読んでみてください。