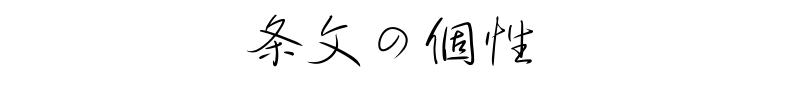動産質の場合は,担保物を使用・収益してはいけないですよね?(民法350条で準用する民法298条2項)
なのに,なんで不動産質の場合は,担保物を使用・収益してOKという,全く反対のルールになっているの?
本記事は,不動産質の場合にのみ,使用・収益が認められる理由について解説しています。
記事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログ管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発合格(202点)した勉強法
参考:4ヶ月で筆者を合格に導いた超厳選の良書たち
読者さんへの前置き
※赤文字は,行政書士・宅建・公務員試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方です
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
結論:不動産という資産価値が高いものが遊休状態にならないようにするため
※担保物権の基礎が不安な方は,先にこちらの記事をご覧ください。 担保物権の横断理解・バックグラウンドを詳しく解説しています。
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
民法356条 【不動産質権者による使用及び収益】
不動産質権の場合,質権者は,担保にとっている不動産を,自由に使用・収益することができます。
解説:動産質・不動産質の対比で理解しておく
動産質・不動産質の条文確認
動産質の場合は,債務者(担保物の所有者)が,債権者が担保物を使用・収益することについてOKと承諾をしなければ,債権者は担保物を使用したりできません。
第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。
民法350条 【留置権及び先取特権の規定の準用】
↓ 準用している条文の中から,298条をピックアップ
1 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
民法298条 【留置権者による留置物の保管等】
↓298条を,『留置権』から『動産質権』へリライト
1
留置権者動産質権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。2
留置権者動産質権者は、債務者の承諾を得なければ、留置担保物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。3
留置権者動産質権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、動産質権の消滅を請求することができる。↓
1 動産質権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2 動産質権者は、債務者の承諾を得なければ、担保物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 動産質権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、動産質権の消滅を請求することができる。
民法298条 動産質権の準用Ver
以上の条文・準用の関係から,動産質権者は,債務者(担保物の所有者)のOKが無ければ,担保物を使用・収益できません。
対する,不動産質権者について,民法356条には,全く違うことが書いてあります。
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
民法356条 【不動産質権者による使用及び収益】
よって,不動産質権者は,債務者(担保不動産の所有者)からOKを貰わなくても,当然に担保不動産を使用・収益できます。
なぜ動産質と不動産質において,使用・収益のルールが違うのか
なぜ,使用・収益について,動産質と不動産質で全く異なるルールをわざわざ設けているのでしょうか?
理由は,不動産という人々の衣食住の拠点になりうる,非常に価値の高い資産を,遊休状態にしないためです。
質権の継続要件として,担保物を債権者が占有し続ける必要があります。
質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
民法342条 【質権の内容】
したがって,債権者が担保物を手元にキープし続けなければいけないので,原則として,担保物は債権者のもとに人質として大切に保管し続けなければならないのが,質権の最大の欠点です。
不動産に質権が設定されたら最後,誰もこの担保不動産を使用できないとなると,その不動産は資産的価値がほぼゼロになってしまいます。
人々の衣食住の拠点になり得る不動産を遊休状態,すなわち,死なせておくことは経済的損失がかなり大きいです。
そこで民法は,わざわざ民法356条を用意し,質権の原則を修正して,不動産質における担保不動産を,債権者が自由に使用・収益できるようにしたのです。
参考文献など
この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。
行政書士合格を目指す方必見!
筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用書籍を無料公開しています。
特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!
最後まで読んでくださりありがとうございました!