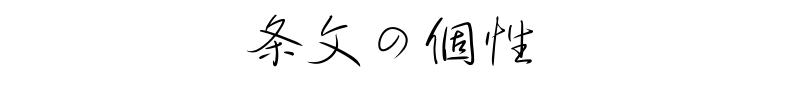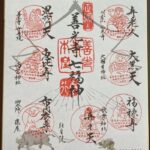テキストや基本書に,『原始取得』や『承継取得』って用語が出てくるけど,それぞれどういう意味なの?
あと,なんで取得時効は原始取得なの?
本記事は,原始取得と承継取得の違いと,なぜ取得時効が原始取得なのか,をわかりやすく解説しています。
記事の信頼性
本記事は,4ヶ月の独学で試験に一発合格した当ブログ管理人の伊藤かずまが記載しています。
現在は,現役行政書士として法律に携わる仕事をしています。
参考:独学・働きながら・4ヶ月・一発合格(202点)した勉強法
参考:4ヶ月で筆者を合格に導いた超厳選の良書たち
読者さんへの前置き
※赤文字は,試験対策として絶対に知っておくべき単語・用語・概念・考え方,その他重要ポイントです
※太文字は,解説中で大切なポイントです
※本記事は,2020年4月1日施行の民法改正に対応しています
結論:原始取得は”前主の権利に基づかない”,承継取得は”前主の権利に基づく”承継
原始取得は,“前主の権利に基づかないで“,権利(所有権など)を取得すること。
承継取得は,“前主の権利に基づいて”,前主が有する権利を,後主が引き継ぎ,承継すること。
取得時効が,原始取得とされる理由は…
取得時効は,前の持ち主がいる・いないは関係なく,時効完成の事実により,前の持ち主の所有権存続が断ち切られます。
この前の持ち主の所有権存続の断絶により,前の持ち主の権利の影響を受けること無く,所有権を取得するという側面を有するためです。
解説:“前主の権利に基づかないで”=“前主の権利の影響を受けないで”の理解が最重要
なぜ取得時効は原始取得なのか
『原始取得』という言葉が持つイメージなのか,更地にマイホームを建てた場合の不動産所有権の取得が原始取得であるという事例の影響なのかは不明ですが,たま~にですが,“原始取得=前の持ち主が存在しない!“と勘違いしてしまっている方がいます。
原始取得の定義を改めて見てみると,『“前主の権利に基づかないで“,権利(所有権など)を取得すること』とあります。
この“前主の権利に基づかないで”ですが,わかりやすく言い換えると
“前主の権利の影響を受けないで”
ということです。
つまり,原始取得とは,“前主の権利の影響を受けないで” 権利(所有権など)を取得することなのです。
例えば,道端でキレイな石ころを拾って,自分の物にしようと持ち帰ったとします。
この石ころが,自然界の物だったなら,前の持ち主が存在しないため,無主物先占となり,“前主が存在しない”ことから,存在しない前主の影響を受けるわけがないので,当然に“前主の権利の影響を受けない”ため,原始取得となります。
一方で,この石ころが,実は誰かの大切なコレクションだったが,紛失したという経緯のある遺失物だった場合を考えてみます。
この場合は,前の持ち主はたしかに存在しますが,拾得者は,前の持ち主との取引行為などで譲ってもらうなどして石ころを手に入れたわけではありません。
たしかに,紛失後も,前の持ち主の所有権は生きていたでしょう。
しかし,新たに自分の物にしようと拾った人が現れたという事実により,前の持ち主の所有権という権利の存続は一旦断ち切られることになります。
よって,前主が存在していたとしても,所有権の存続を断ち切られたのだから,“前主の権利の影響を受けないで”後主が所有権を手に入れたとして評価され,遺失物の拾得は原始取得となります。
このとおり,改めて考えてみると,原始取得には,前主が存在するパターン(無主物先占)と,存在しないパターン(遺失物の拾得)とがあることがわかります。
すなわち,原始取得か承継取得なのかという区別は,前の持ち主が存在するかしないかではなく,所有権などの権利取得が,“前の持ち主の権利の影響を受けるか否か”という観点での区別なのです。
ここまで来たら,「なぜ取得時効が原始取得なのか?」の理解まであと一歩です!
取得時効は,状況的には,前の持ち主が存在します。
しかし,取得時効による所有権の取得は,前の所有者から契約によって売買したものでも,譲渡してもらったものでもありません。
ここで,取得時効の完成という事実により,前の持ち主の所有権の存続は断ち切られ,新たな所有者が所有権を手に入れるという,時効制度の側面が顔を覗かせます。
上記を勘案すると,取得時効の取得は,原始取得と承継取得のどっちなのか,というと,原始取得に分類されることが自然なカテゴライズといえます。
以上から,前の持ち主がいる・いないは関係なく,時効完成の事実により,前の持ち主の所有権存続が断ち切られ,“前の持ち主の権利の影響を受けないで”所有権を取得するという側面を持つ取得時効は,原始取得であると言えるのです。
原始取得と承継取得の具体例整理
ここからは,原始取得と承継取得のそれぞれに,どのようなものが分類されているのかを,ざっくりと整理しておきます。
原始取得の具体例:無主物先占・遺失物や埋蔵物の拾得・時効取得
(しつこいですが)原始取得は,前主の権利に基づかないで,新しく権利(所有権など)を取得することです。
前主の権利の影響を受けず,新しく所有権などを手に入れるため,手に入れる権利には余分な権利(抵当権・質権など)は付着せず,完全な状態の所有権などを手に入れることになります。
原始取得には大きく3つ種類があり,それぞれ以下のとおりです。
- 無主物先占
- 遺失物や埋蔵物の拾得
- 取得時効
無主物先占
道に落ちている石を拾った場合や,四つ葉のクローバーを見つけて持ち帰ったときに,自分の物にすると決めた場合,これらの石や四つ葉のクローバーの所有権を手に入れることができます。
これは原始取得の,無主物先占と言われるものです。
遺失物や埋蔵物の拾得
他人の落とし物や埋蔵物を手に入れた場合に,一定期間持ち主が現れないなど,特定の条件を満たすと所有権を取得するのも原始取得の一種です。
取得時効
原始取得において,一番試験で問われるのが,取得時効です。
一定期間物を占有し続け,民法162条に規定される要件を満たすと,取得時効により,その物の所有権を手に入れることができますが,この取得時効は原始取得とされています。(取得時効が原始取得に分類される理由は,前述のとおりです。)
したがって,取得時効によって手に入れる物に,抵当権や質権や地役権がくっついていたとしても,原始取得である取得時効によって手に入れる所有権は,それらの余分な権利が付着していない完全な所有権となります。
※取得時効の要件(民法162条)については,こちらの記事で解説しています。 併せて読んでみてください!
承継取得の具体例:売買などの契約に基づく取引・相続
承継取得は,“前主の権利に基づいて”,前主が有する権利を,後主が引き継ぎ,承継することです。
前主の権利を引き継ぐので,前主の所有権に付着していた権利(抵当権など)も,そっくりそのまま後主に引き継がれます。
承継取得は,以下の2つが主な例で,特定承継なるものと,包括承継なるものが存在します。
- 売買などの契約取引(特定承継)
- 相続(包括承継)
※特定承継・包括(一般)承継については,こちらの記事で解説しています。 人気記事です!併せて読んでみてください!
契約取引(特定承継)
売買や贈与などの,契約行為によって所有権を譲渡する取引は,承継取得です。
相続(包括承継)
相続による,被相続人の権利や立場を一切合財全て丸ごと承継する相続は,承継取得です。
参考文献など
この記事は以下の書籍を参考にして執筆しています。 より深く理解したい方は以下の基本書を利用して勉強してみてください。 必要な知識が体系的に整理されている良著なので,とてもオススメです。
行政書士合格を目指す方必見!
筆者が,行政書士試験に,4ヶ月の独学で・仕事をしながら・202点で一発合格したノウハウや勉強法,使用書籍を無料公開しています。
特にノウハウ集は,有料note級の1万2000文字以上の情報量で大変好評なので,是非読んでみてください!
最後まで読んでくださりありがとうございました!